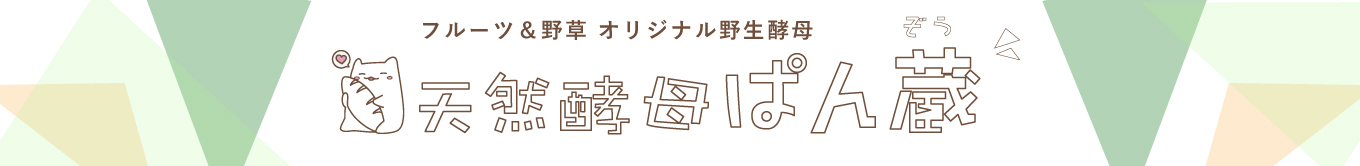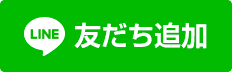パンの中に何か具材が入っているお総菜系のものや、
クリームなどが入っているお菓子系はみんなの人気ですね。
特にお子さんは大好き。
お店に言っても必ずトレーの中に入れたがるんじゃないでしょうか^^
そんな具材が入っている美味しそうなパン。
今日はそんな生地の中に入れる具材のお話をしようと思います。

天然酵母ぱん蔵の 椿留美子です。
お山での田舎暮らしを実践、発酵生活をしています。
そんな暮らしを踏まえながら、東京と山梨で自家製酵母を使って、
発酵器を使わない、ほったらかしの「ゆるパン」教室を2009年より始めました。
現在は仕事で使いたい方、深く極めたい方向けのプロ向け講座をやっています。
ラインで直接お問い合わせはこちらから
このお話を動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
フィリングとは?
レシピの中に【フィリング】という言葉が書いている時があります。
「え、フィリング?」
「なんだそれは?」
と思われている方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
まあ読んでいくと、なんとなく感覚でパンの中に入れる中身のことかな〜、
というイメージで捉えているのではないでしょうか。
実は私がそうでした(笑)
人ってなんとなくの感覚でとらえることって結構ありますよね。
パンにおけるフィリングというのは、
生地の中に入れたり間に挟む具材のことを指します。
お菓子においても同じような意味で使われます。
フィリングは生地とその中身の具材が一体化したもので一つの作品が成り立つので
とても重要な役割を果たします。
生地が美味しいのに中身の味が今ひとつ・・・
とか、逆に中身の味付けはとってもいいのに生地が美味しくない・・・
などどちらが優っていてもバランスが悪いものです。
パン作りをする人は生地作りを一生懸命しがちですが、
中身もとても重要なポイントになりますのでここはしっかり頭に入れておきたいところです。
天然酵母パンにフィリングを入れるって難しい?

手作りパンにフィリングを入れるのって、
ちょっと緊張しませんか?
私はかつて、何度も
「はみ出た」
「流れた」
「破れた」
パンたちをオーブンから救出してきました(笑)。
フィリングを入れると生地が破れたり、焼いている最中に中身が飛び出してきたり…。
「美味しそうに見えるどころか、なんか…大惨事?」
そんな経験、パンを作る方ならみなさんあるかもしれませんね
よくある失敗:「はみ出る・破れる・流れ出す」
これは本当に多くの方が経験する失敗で、私自身も何度も繰り返しました。
特に水分が多い具材(カスタードやフルーツ煮など)を入れた時は、
焼き途中に中身がブシュッと出てしまって台無しに…。
教室の生徒さんからも
「包んだはずなのに、焼き上がったら中身がどこかに行ってる!」
という声をよく聞きます。
なぜ天然酵母パンはフィリングが難しいのか?
それにはいくつか理由があります:
- 天然酵母の生地は弾力を残して作るものが多く、扱いづらい
- 発酵に時間がかかるため、具材と生地の状態を見極める必要がある
- イーストパンに比べてどっしりと焼き上がるパンが多いので、発酵時間がうまくいってないとひび割れがしやすくそこから漏れやすい
この「繊細さ」と「時間差」を理解し、
適切に扱うことが、フィリングパン成功のカギになります。
フィリングに向いている具材・向かない具材とは?
おすすめ具材とその理由(プロ視点で)

私が実際に使って良かったフィリングは以下のようなものです:
- あんこ(こし・粒):水分が少なく包みやすい。
- クリームチーズ:コクが出て、生地との相性も抜群。
- ドライフルーツ(ラムレーズンやクランベリー):水分を吸った状態で混ぜ込むとバランスがいい。
- ナッツ類:香ばしさが加わり、食感のアクセントになる。
これらは焼成中に流れ出す心配が少なく、初心者にもおすすめです。
NGになりやすい具材の特徴と失敗例
- 生の果物(リンゴ、桃など):水分が出てベチャッとなる。
- 水分の多い野菜(トマト、ズッキーニなど):焼いている最中に水が生地に染み出しやすい。
- 加熱不足のクリーム類:焼成中に溶けて流れ出ることも。
私がかつて失敗したのは、「手作りカスタードを包んだパン」。
見た目はきれいに包めたのに、焼成中にドバーッと溶け出してきて、
鉄板が焦げカスタードだらけに…(苦笑)

フィリングをきれいに包むコツ|形が崩れない成形術
「均等に包む」コツとイメージ法
生地を広げてフィリングを置くとき、欲張らずに中央に少量ずつがポイント。
特に天然酵母生地は、弾力があり伸ばしすぎると生地が傷みやすいので注意が必要です。
↓ 生徒さんの失敗あるある ↓
✅ 生地の伸ばしが足りなくて包みきれない
→包み切れる大きさに広げて生地を丁寧に伸ばしながら包む
✅ 生地を薄く伸ばしすぎて破れる
→「広げすぎない」「具材は真ん中に」指導

あとは閉じしろの部分に具材が付かないようにするのが大切です。
ここがうまくいかないと包めなくなります!
発酵の見極めと焼成のタイミング
- 過発酵だと生地がゆるくなり、フィリングが重みに負けて底抜けしやすい
- 発酵不足だと膨らみが足りず、包み目が開きやすい
発酵の見極めは、表面の張り具合や生地の膨らみの様子で判断してみてください。
フィリングパン販売・教室で気をつけたいこと
販売向けに注意が必要な具材とは?

- 要冷蔵が必要な具材:販売時に温度管理が難しくなる
- アレルゲン表示が必要なもの(ナッツ、卵、乳製品など)
- 時間が経つと劣化しやすいもの(クリーム系)
実際、イベント販売の際に「カスタード系は早めに召し上がってください」と注意書きを添えたことがあります。
時期にもよりますが、夏場の販売には注意が必要ですね。
おまけ:フィリングありパンの保存は?冷凍・解凍方法
- 完全に冷めてから1個ずつラップに包む
- ジッパー付き袋で空気を抜いて冷凍
- 解凍は自然解凍後、トースターで軽く温め直す
この工程を丁寧に行うことで、フィリングパンでも美味しさを保ったまま保存できます。
まとめ|フィリングは天然酵母パンの「魅せポイント」になる

パンの中でもフィリングパンは
見た目のワクワク感と、食べた時の驚きが一度に味わえるから人気ですね。
「これ、手作りなの!?」
と手作りのフィリングはやはり美味しい!
自分好みに作れるのも魅力ですね。
生地と具材が一体となったパンは、作る楽しさも食べる楽しさも倍増します。
コツさえつかめば、天然酵母でもしっかり包んで、
美味しさもビジュアルも兼ね備えたフィリングパンが作れますよ♪