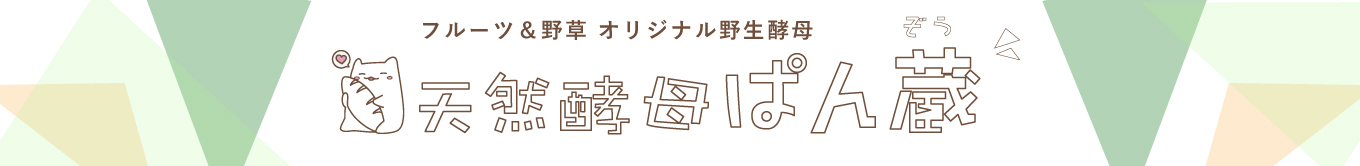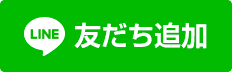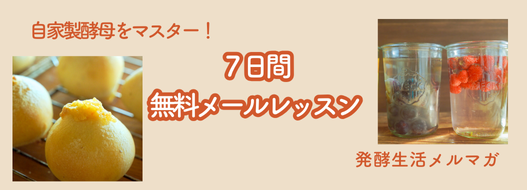「クープは開かないのに底が割れてしまう…」
そんなお悩み、ありませんか?
この記事では、自家製酵母パンで起こりやすい
“底割れ”の原因を3つの視点――
「生地の種類」
「ベンチタイム」
「二次発酵」
から詳しく解説していきたいと思います。
パン作り初心者〜中級者の方にも分かりやすく、
今日から実践できる具体策を紹介します。

天然酵母ぱん蔵の 椿留美子です。
お山での田舎暮らしを実践、発酵生活をしています。
そんな暮らしを踏まえながら、東京と山梨で自家製酵母を使って、
発酵器を使わない、ほったらかしの「ゆるパン」教室を2009年より始めました。
現在は仕事で使いたい方、深く極めたい方向けのプロ向け講座をやっています。
ラインで直接お問い合わせはこちらから
パンが底割れするのはなぜ?生地・ベンチタイム・二次発酵から見直す3つの原因と対策
「クープはうまく開かないのに、底だけがバリっと割れる…」
「きれいに焼きたいのに、毎回どこかが割れてしまう…」
そんな経験、ありませんか?
先日、生徒さんからこんな感想をいただきました。
「パンを焼くときに変なところから割れてくる時と、割れないできれいに焼ける時があります。
これは何の違いがあるのでしょうか?」
実は、パンの“底割れ”にはいくつかの明確な原因があります。
とくに、自家製酵母パンの場合は発酵の見極めや生地の状態を丁寧に観察することが、
見た目にも美しいパンに仕上げるカギとなります。
今回は、実際にいただいた生徒さんの質問をきっかけに、
「底割れ」の原因と対策を3つの視点から解説していきます。
パンの底が割れる、横からのひび割れ…それ、何が原因?
自家製酵母パンを焼いていて、こんな状態になったことはありませんか?
形がいびつになって、底がベリッと割れている
焼成後に持ち上げると、底が変形していたり、割れていたりする
成形時はうまくいったのに、焼き上がりが納得できない
なぜこんなふうになってしまうのでしょうか?
以前にもブログに書いたことがありますが、今回はまた違う視点から解説してみたいと思います。
“底割れ”を放置すると、パンの完成度が一向に上がらない

底割れを「たまたまかな?」とそのままにしてしまうと…
原因がわからないままで繰り返してしまう
次回の焼成に不安が残る
販売やレッスンで「仕上がりに自信が持てない」という悪循環に…
特に教室運営や販売を目指している方にとっては、見た目の美しさも大きな価値になります。
つまり、原因を知らずにいるということは、
再び繰り返してしまい、教室をやったときに
生徒さんにも説明できないということになってしまいます。
底割れを防ぐために見直したい、3つのポイント
では、底割れを起こさないためには何を見直せば良いのでしょうか?
実際に多くの方がつまずいているのは、以下の3つです:
生地の種類(配合・水分量・粉の特徴)
ベンチタイムの取り方(温度・時間・生地の緩み)
二次発酵の見極め(過発酵・不足の判断)
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
① 生地の種類が底割れに影響する
使用している粉や水分量、生地の硬さによって、オーブン内での膨張の仕方が変わります。
特に以下のような生地は、底割れが起こりやすくなります。
ハード系で水分量が少なく締まりすぎた生地
粉の特性を無視して強引にまとめたレシピ

💡対策:
生徒さんのお話を聞くと、
割とやわらかめの生地の場合はうまくいっていて
固めの生地の場合に割れてしまう・・という現象が起こりやすい
ということでした。
固めの生地は割れやすくなります。
どっしり感のあるパンを焼きたいときは特に注意が必要です。
そんな生地の場合は
✅ コネをしっかりする
✅ 発酵を多めにとる
✅ ベンチタイムを長めにとる
✅ 2次発酵をたっぷりとる
これらを頭に置いてやってみていただくといいかと思います。
② ベンチタイムの取り方がパンの展開を左右する
ベンチタイムは「休ませる時間」と思われがちですが、
実はとても重要な生地の緩和・ガス調整のステップ。
ここが短すぎたり、逆に長すぎたりするのはよくありません。
特に今回のテーマの「底割れ」では、ベンチタイムの時間が短いと起こりやすくなります。
生地が締まったままで焼成時に逃げ場がなくなる
成形がやりにくく、きちんととじ目が閉じられていない

💡対策:
ベンチタイムの生地は指で軽く押して少しガスがたまって、
生地がふわっと緩んできているか見極める。
生地の温度や室温によって調整する柔軟性も大切です。
③ 二次発酵の見極めが甘いと、底割れにつながる
これは本当に多い失敗です。
「そろそろいいかな?」という勘で焼き始めると、
生地の緩みが足りなくてガスが膨張するのに耐えられず、割れてきてしまいます。
特に自家製酵母は市販イーストに比べて発酵の進みが読みにくく、
見極めの感覚を養うことが重要です。

💡対策:
発酵カゴを使う場合、外す前に
指の跡が残る程度の「柔らかさ」くらいで焼成に入ると、
膨らみが落ち着き、底割れしにくくなります。
“底割れを直したい”と思ったあなたは、確実にパンの技術が伸びています!
底割れに悩むということは、すでに“焼き上がりの完成度”に意識が向いている証拠です。
「生地の扱いが適切か?」
「成形のとき、無理をしていないか?」
「発酵の見極めはどうだったか?」
そうやって見直す癖がついてくると、感覚がどんどん洗練されていきます!
過去に別の視点から「底割れ、ひび割れ」について書いたブログもあります。
ぜひ参考にしてください!
パン 割れる – 焼成時に横割れ、底割れしてしまう そんな時にチェックしたい5つのポイント
もっと深く学びたい方へ:メルマガで発酵の“感覚”を学びませんか?
私のパン教室では、こうした
**“原因がはっきりしない失敗”を丁寧に言語化し、どうすればうまくいくか**
を自分で考える力をつけてもらっています。
✅ 発酵の微妙な見極め方
特に自己流ではなかなか伝わりにくい部分です。
無料メルマガで、ぜひ学習してください!
パン作りや酵母作りのポイントをお届けしています。
まとめ「パンの底割れ」は、技術向上のチャンス!
底割れの原因は「焼成だけ」でなく、
生地の種類・ベンチタイム・二次発酵
といった工程にヒントがあります。
一つずつ見直していくことで、あなたのパン作りは確実に変わります。
そしてその積み重ねが、
「売れるパン」や「教えられる技術」
につながっていくのです。
焦らず、一歩ずつ。
一緒においしいパンを目指しましょう。