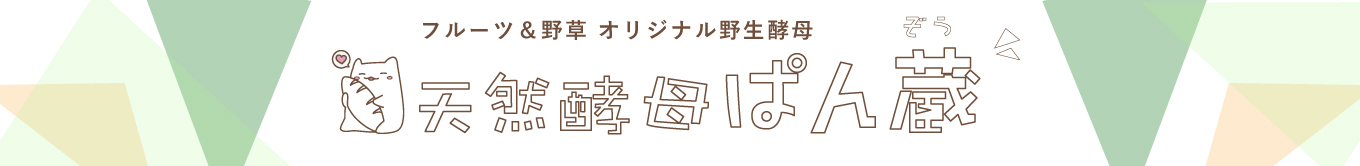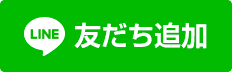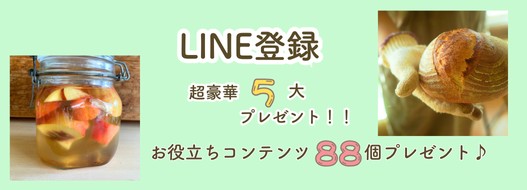こね上げ温度、って聞いたことありますか?
パン作りのノウハウ本には、よく出てくる言葉かもしれません。
今回は
「自家製酵母パン作りとこね上げ温度の関係」
について、私なりの考えをお話してみたいと思います。
************** 
天然酵母ぱん蔵の 椿留美子です。
お山での田舎暮らしを実践、発酵生活をしています。
そんな暮らしを踏まえながら、東京と山梨で自家製酵母を使って
発酵器を使わない、ほったらかしの「ゆるパン」教室を2009年より始めました。
現在は仕事で使いたい方、深く極めたい方向けのプロ向け講座をやっています。
ラインで直接お問い合わせはこちらから
こね上げ温度がパンの出来を左右する!自家製酵母パン作りで失敗しないための温度管理のコツ
このお話を動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
パン作りにおける「こね上げ温度」とは?
パン作りにおいて
「こね上げ温度」
という言葉を耳にしたことがありますか?
実は、私はたいして気にしていません。
ですのでおそらく
私のレッスンに来てくださっている生徒さんは
「聞いたことない〜〜〜〜」
という方が多いかも (^ ^;
「こね上げ温度」は重要か?!
これはあくまでも私の見解ですが
天然酵母パンを長年作り続けている経験から、お話をしたいと思います。
発酵工程で違う、理想的な温度?!
こね上げ温度とは
こね上がったパン生地の温度のことを指します。
パン作りではこの”こね上げ温度”が
生地の発酵スピードや風味、膨らみ
そして、最終的なパンの仕上がりに影響を与えます。
私が初めてパン作りを始めた頃
この「温度」の大切さを、まったく意識していませんでした。
季節が変わると、生地の状態が違ってくるんですね。
それって生地の温度の影響だったんだ!
と気づいたのです。

レシピ本などで一般的に書かれている、パン生地のこね上げ適正温度は
26~28℃くらい
ではないかと思います。
生地の種類によって(バターの多いものやハード系など)
多少変わってきます。
「こね上げ温度はパンの味に関わってくるから重要です」
というようなことも言われたりします。
手ごねか、機械ごねかによっても
出来上がりの温度が変わってきます。
生地の温度を測るの?
そんなことまでしなくちゃパンは作れないの??
なんて面倒くさい・・・・・
と、そんな注意書きを見た日には挫折する方も少なくありません。
私が最初に習った、家庭のキッチンで開催されているパン教室は
ゆるーい感じで楽しく作ることができたので
「パン作りって楽しい ^ ^」
って思うことができました。
最初の体験ってめちゃくちゃ重要ですね!!
ちょっと余談でしたが・・
さて、その重要視されている”こね上げ温度”
どう考えたらいいのでしょうか?
多くのパン作りの工程は
生地作り(こね)→ 一次発酵
と進みます。
その一次発酵をスムーズに行うために
こねの段階で 生地の温度が適正であるほど、うまくいきます。
温度が高すぎると過発酵になるし
低すぎるとなかなか発酵しない、 ということになります。
発酵温度や時間がレシピでは決まっているので
その通りにやろうと思ったら
どうしても、生地の温度が必要になってきます。
つまり
工程通りやるための大切な数値
ということになります。

一方、自家製酵母でパン作りをする際に
私のレッスンでは、”長時間発酵”をおすすめしています。
長時間発酵は
低温の状態で長い時間をかけて発酵させていきます。
その時の生地は、低温にしなければいけません。
となると生地の適温は関係なくなります。
むしろ、冷やさなくてはいけないということになります。
もうお分かりのように、そこまで
こね上げ温度は気にしない
のです。
ただし、機械ごねの時は生地の温度が上がりやすいので
注意が必要な時があります。
一旦上がってしまうと
膨らみや味に影響が出ることがあります。
温度が低すぎるとうまくこねられないので
こちらはまず大丈夫だと思います。
つまり、よっぽどの高温には注意が必要ですが
多くの場合は
細かい数値は気にしなくて大丈夫!
ということです。
生地をこねる、ということに関しては
温度についても大切なことがあります。
次に、そのことについてお話します。
*長時間発酵について気になる方はこちらをご覧ください。
冷蔵庫での長時間発酵ではどうしても固くなってしまうという方に、ふわふわに仕上げるポイント
冷蔵庫を使ったパン生地の長時間発酵のポイント、プロが教えるとっておきのやり方 オーバーナイト
これからお話することは
普段の私がやっていることとはちょっと違います。(それをご承知おきください)
これをお勧めする方は
・ドライイーストでパン作りをする方
・一気にパン作りをしたい方
・時間通りに大量生産したい方
あとは
理論的に知っておきたい方、でしょうか。
そういう方は、ぜひ参考にしてみてください!
高すぎるこね上げ温度が引き起こすトラブルとは?
夏場のパン作りでありがちな失敗
夏になると
「いつもの通りに作ったのに、なんだかだれる…」
と感じたことはありませんか?
私も教室でよくいただく相談のひとつが
”夏になると急にパンが上手くできない”
というお悩みです。
実はこれ
こね上げ温度が高くなりすぎている
のが原因なんです。
パン生地は、26℃〜28℃くらいが
最も安定して発酵しやすい温度帯ですが
夏場に普通に作ると、簡単に30℃を超えてしまいます。
そうすると発酵が一気に進み
生地がゆるんだり、風味が浅くなったりするんですね。
私もかつて、真夏にパンをこねていたら
生地温度が32℃に…。
予想以上に発酵が進み
焼き上がりのパンが、”スカスカ”になってしまったことがありました。
こね過ぎで生地温度が上がるメカニズム
ミキシングや手ごねを長く続けると
生地は摩擦で温まり、温度がどんどん上がります。
これを意識せずにこねすぎると
狙っていないこね上げ温度
になってしまうのです。
特に、家庭用のスタンドミキサーでは
モーター熱も加わって
思った以上に温度が上がりやすい傾向にあります。

理想的なこね上げ温度の目安(季節別)
それでは
季節に応じた理想的なこね上げ温度を見てみましょう。
| 季節 | 理想のこね上げ温度 |
|---|---|
| 春 | 22〜24℃ |
| 夏 | 20〜22℃(低め) |
| 秋 | 22〜24℃ |
| 冬 | 24〜26℃(高め) |
この温度を意識するだけで、発酵の安定感が違ってきます。

こね上げ温度をコントロールするための3つの実践テクニック
1. こね上げ温度と仕込み水の関係をチェック

先ほど
こね上げ温度は気にしない
ということを言いましたが、
こねる時には気にした方がいい場合があります。
例えば暑い時期は
生地が緩みやすい→温度が上がりやすい
寒い時期は
生地がなかなか伸びない→うまくこねられない
ということがありますので、工夫が必要です。
そのために
仕込みに使う水(お湯)で調整していきます。
これを使うことによって
こね上げ温度も変わってきます。
ドライイーストを使う場合や天然酵母でも
早く発酵させたいときは
”仕込み水とこね上げ温度”は、チェックしておいた方がいいかと思います。
仕込み水については、こちらもご参考にしてください。
仕込み水とこね上げ温度 – 仕込み水の温度って気にしなきゃいけないの?パン生地のこね上げ温度との関係を解説
2. こね時間を短くする(特に夏)
温度の上昇を防ぐために、こねすぎない工夫も大切です。
私は夏場は
「オートリーズ法」を取り入れることもあります。
そうすることで、こね時間を短くしています。
*オートリーズ法は粉に水分を加えてしばらく置いてグルテンを引き出す方法です。
3. 材料や道具類を事前に冷やす もしくは 温める
季節によって対応が変わってきます。
暑い時期は「冷やす」
寒い時期は「温める」、のが基本です。
例えば
粉を冷蔵庫で冷やす(夏)
仕込みボウルや道具をあらかじめ冷蔵庫で冷やす(夏)、または温める(冬)
氷水を使う(夏)
こうした小さな工夫も有効ですね。

こね上げ温度を記録するとパン作りはもっと上達する!
習慣としてのご提案は
パン日記をつけること!
特に温度に関するデータは、記録してもいいかもしれません。
記録しておくべきポイント
室温
粉温
水温
こね上げ温度
発酵時間と状態
こうして記録を残すことで
「季節ごとのベスト温度」が見えてきます。
たとえば
「真夏は21℃がベスト」とか
「冬は25℃くらいが膨らみやすい」といった
”自分のレシピ”ができてくるんです。

自家製酵母パン作りのこね上げ温度の考え方

自家製酵母パン作りにおいては
”長時間発酵”が美味しいと思っています。
私がパンを作るときは
こねたその日に焼くことは、まずありません。
1日から数日寝かすこともあります。
その時に冷蔵庫を使うこともあるし
寒い時期は、そのまま室温でおいておくこともあります。
そうです、これがぱん蔵の
♪ほったらかしパン作り♪
の原点です。
特に忙しい生徒さんには
「楽に作れる〜〜〜」
と好評です ^ ^
低温でじっくり長時間発酵をやっていく場合は
あまりこね上げ温度を意識しなくても大丈夫です。
低温発酵したい時に
ニーダー(こね器)でこねて温かい生地になった場合 、急冷することもあります。
発酵を促したくない時、です。
そんなふうに調整していきます。
ドライイーストのパンをやっている方に言うと
数日生地を寝かせる、というのは驚かれます。
自家製酵母と国産小麦ならではの
「旨味製法」かもしれませんね ^ ^
こね上げ温度がパンの出来を左右する!パン作りで失敗しないための温度管理のコツ まとめ
いかがでしたでしょうか?
こね上げ温度に関しては
いろいろな考え方があると思います。
どれも美味しいパン作りを考えての考え方なので
これが絶対正しい!
ということはありません。
私は今までの経験からお話しましたが
もっといいやり方があるかもしれません。
自分が絶対、という考えはなく
いろんな角度から、まだまだ検証、実験していきたいです。
これを読んでくださった方も
ご自分の一番やりやすい方法と、うまく行った経験を活かしてやってみてくださいね。
迷っている方へ
少しでもご参考になれば嬉しく思います。
LINE公式アカウントでお悩み解決動画をプレゼント中!
パン作り、酵母作りのお悩み
季節に合わせた具体的な方法など、LINE登録でプレゼントしています。
ぜひご登録くださいね♪