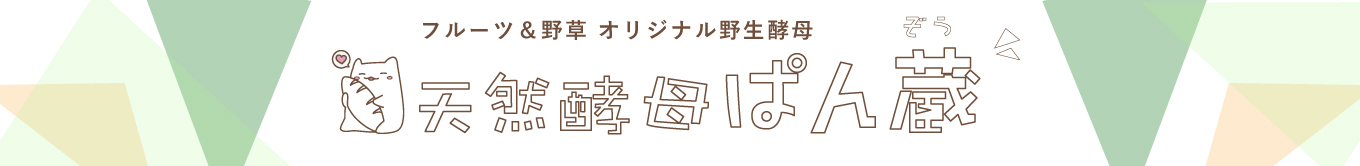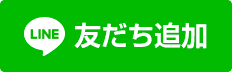「常在菌」という言葉は聞いたことありますか?
主にヒトの身体に存在する微生物のうち、多くの人に共通してみられ、病原性を示さないものを指す。
(ウィキペディアより)
常在菌とは私たちの身体にいる菌のことなんですね。
空気中にも浮遊している菌がいます。
それももちろん私たちの暮らしに影響を与えています。
今日はそんな「菌」のお話をしてみたいと思います。
**************
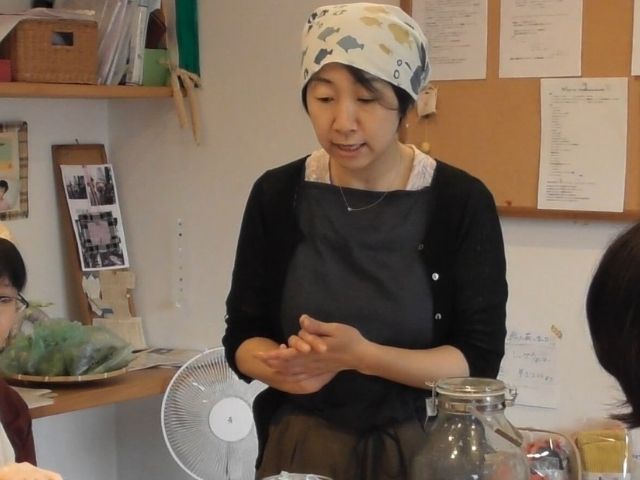
天然酵母ぱん蔵の 椿留美子です。
お山での田舎暮らしを実践、発酵生活をしています。
そんな暮らしを踏まえながら、東京と山梨で自家製酵母を使って、
発酵器を使わない、ほったらかしの「ゆるパン」教室を2009年より始めました。
現在は仕事で使いたい方、深く極めたい方向けのプロ向け講座をやっています。
酵母 菌 パン – 酵母菌、常在菌の力 パン作りにおいてどう関係してくるのか考えてみる
この話を動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
教室で作る時と自宅で作る時の違い、感じますか?
先日、東京のレッスンがオンラインレッスンに変更になりました。
オンラインレッスンでは、通常の対面レッスンのように焼いたパンを
食べていただくことができません。
それがちょっと残念なのですが、いいこともあります。
レッスン中にみんなでこねて、それをレッスン後に
お家で発酵させて焼いていただくんですが
その過程をやりとりしてアドバイスしていきます。
(通常のレッスンではお家で焼く過程まで細かく見ていません)
それぞれのお家の環境によって発酵の状態も変わってくるからです。
オーブンによっても焼き方に違いが出てきます。
同じようにやっても、うちでやるのとそれぞれのご家庭でやるのとでは
違いが出てくることに改めて気付きます。
これまで全体的にみてきて、さまざまなパターンがありますが、
今日はその一つのことをテーマにお話をしてみたいと思います。
酵母菌が住み着く
パン屋さんが新装開店した時に、
「最初はうまく焼けないけど、だんだんいつもの感じで焼けるようになってきた」
と言われることがあります。
それは、新しい器具(オーブンなど)に慣れていなかったりという事が考えられます。
しかし、まだ原因はあるのです。
それは何かというと
早く酵母菌が増えてくれないかな
という事です。
空気中にはさまざまな菌があります。
え、菌がいるの?!
とびっくりしないでください。
私たちは大昔から菌と共生しています。
その中でもパンを焼く回数が多い工房の中には
酵母菌がたくさんいるということになるのです。
その菌たちはパン作りに影響してきます。
酵母菌との共生はパン作りの常識?!
昔、パンを習っていた何人かの先生も口を揃えておっしゃっていました。
「早くおうちに酵母菌が増えるといいね」
そうすると美味しいパンが焼けるようになる、というのです。
これって科学的に証明されているのかは分かりません。
(そういう論文とかあるのかしら??)
でもパンの先生の中の常識なのかなー、って当時は思っていました。
ある先生は、引っ越してきたばかりのおうちに、
レーズ酵母をたくさん作ってうちのいろいろな場所に置いたそうです。

ベテランの先生にこんなことを言われたこともあります。
「たくさんパンを作っているから、椿さんところのお子さんは元気でしょう。
菌がたくさんいると身体も元気になりますよ」
へー、ほんとかな?・・・
とこれこそ、科学的な根拠があるかは不明ですが、あり得るかもと思いました。
菌と仲良くする たくさんの例を見てきて感じたこと
よく言われるのは、
「教室で焼いた方が美味しい」
「うちだと発酵がうまくいかない」
焼くことに関してはオーブンの違いがありますから仕方ないかもしれませんが、
発酵がうかまくいくかどうかは
酵母菌の影響も大きいのではないかと思っています。
何年も通われてうちでもしょっ中作っている方は、
もちろん「慣れ」もあって発酵もうまくいってます。
これは
「見極める力」
「酵母菌の力」
との相互作用なのではないかと思っています。
そして、菌との共生と言えば酵素ジュースを作る時の常在菌です。
酵素ジュースと呼ばれるものは実際のところ
「発酵ジュース」というものです。
果物などの素材を発酵させてその発酵液を飲むジュースです。
シュワシュワしてます。
作り方は出来上がるまで素手で混ぜていきます。
発酵させるのに私たちについている常在菌の力を借りていく、という作り方です。
初めてこの話を聞いたときには驚きましたが
(まさか自分たちについている菌でジュースを作るなんて・笑)
良い菌を増やしていく、とうことなんですね。
手ごねだと常在菌がたっぷり入り込むことになりますね。
想像するとちょっと抵抗ある・・・
という方もいらっしゃるかもしれませんが
それで生地が腐敗するということはありません。
同じ生地でも一人ひとりのパンが違うのはここでも影響があるということになります。
菌との共生は味噌や醤油作りにも影響している

菌の話はパンやジュースばかりではありません。
味噌や醤油の方がむしろ有名な話かもしれません。
老舗の味噌蔵や醤油蔵には建物自体に菌が住みついています。
これは多分その業界の常識になっていると思います。
その菌のおかげでいい熟成ができるのだと。
100年以上も続いているような醸造元だと、もうそこでしか出せない味になるのでしょう。
それってすごいことですよね。
それを考えると、それぞれのうちに住み着いている菌によって
パンにも影響を与えているのでは、という話も納得がいきます。
酵母 菌 パン – 酵母菌、常在菌の力 パン作りにおいてどう関係してくるのか考えてみる まとめ それぞれの環境の違い
今回のオンラインレッスンでもそれぞれの家でやってみた報告をいただきました。
そこで感じたことは、教室で作っている感じと、生徒さんのお家で発酵させていく感じが
それぞれ違っていて、改めて「環境の違い」について考えました。
自分がやっている通りだけではなく、いろいろなパターンを想定して考え、
もっと分かりやすい言葉で、丁寧に伝えていかなければということです。

何回も何回もやってみて「経験」と「菌」を増やしていくんだなあ、と思います。
特に自然発酵の場合はそうですね。
自然発酵は難しい面もありますが、そこが魅力で面白いとも言えます。
慌てずのんびりとやっていきましょう。
手洗いもやりすぎるとかえって風邪を引きやすい、とか
ウィルスが入り込みやすい、とか言われます、
これは常在菌の力ということになります。
ある自然育児を推奨している小児科の先生は
「手を洗わない」「うがいもしない」
ということをすすめています。
身体を守ってくれている菌を排除してどうするんだ、というのです。
ええー!と目からウロコです。
でもこうやって菌との共生、常在菌のことを考えるとなんだか納得。
他のお医者さんで
「石鹸を使わないで流水で10秒」
を推奨している方もいらっしゃいました。
いろいろな考え方があるのですね。
最終的にはご自分で判断されてやっていくのが一番です。
私たちには選択の自由があるのですから ^ ^
今日も読んでくださってありがとうございました。