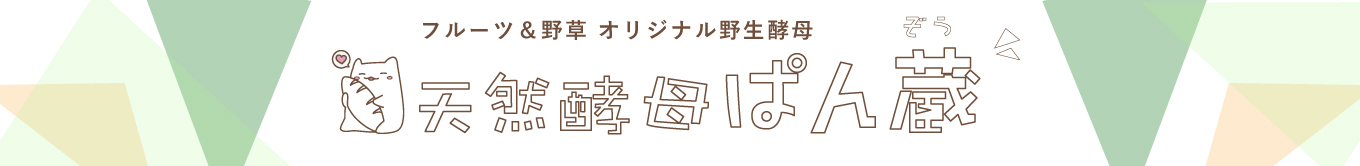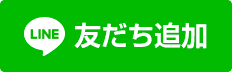天然酵母のパン作りをやっていて、
これは美味しい!!
という作り方ってあるんですよね。
その一つの方法「オーバーナイト法」というのを今日は説明してみたいと思います。
と言っても、私が普段言っていることなのでブログをよく読んでくださっている方は
「なーんだ」ということになるかもしれません・・・(^^;
「え、それ何??」
と思われた方、どうぞお付き合いください^^
**************
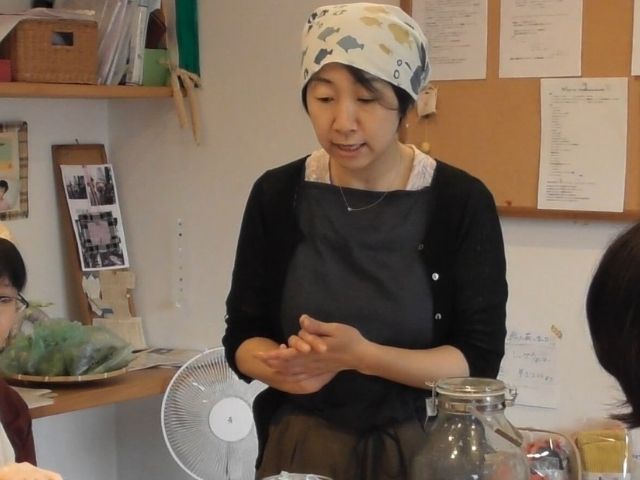
天然酵母ぱん蔵の 椿留美子です。
お山での田舎暮らしを実践、酵母生活をしています。
そんな暮らしを踏まえながら、東京と山梨で自家製酵母を使って、
発酵器を使わない、ほったらかしの「ゆるパン」教室をやっています。
オーバー ナイト パン – オーバーナイト法の失敗しない3つの注意点 生地に旨味を出す製法のおすすめを天然酵母パン講師が解説します
このお話を動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
オーバーナイトって何?
パンを作り始めると、いろいろな専門用語やその世界の独自の言葉をきく機会も増えていくと思います。
ぱん蔵はレッスンの中でもあまり専門用語は使わないので、
何かを調べたときに「これってどういうこと?」と思われることがあるかもしれません。
しかし、専門用語を使わなくても日常の言葉で説明していることがたくさんあるのです。
ご自分の生活の中で楽しむ「パン作り」に関しては難しげな専門用語を使って説明するよりも、
わかりやすい日常のことばで説明した方が頭に入りやすいかな、と思っています。
その中で今日ご紹介する「オーバナイト」。
このブログをみてくださっている読者の方には聞き慣れないかもしれませんが、
実はオーバーナイトって低温で長い時間発酵させる方法のことです。
長時間低温発酵とか冷蔵庫発酵とかのことで、このブログでもよくご紹介していて
いつもやっていることなのです。
その言葉をそのまま捉えると、一晩寝かせる発酵の方法ということになるでしょうか。
前日にこねておいて冷蔵庫に入れ、翌日焼いていく、というイメージです。
日をまたいでパン作り、というふうに思っていただくといいかもしれません。
低温でゆっくり発酵させるので、冷蔵庫をうまく使っていきます。
冷蔵庫を使った作り方はこちらの記事にも書いていますのでご参考にどうぞ。
冷蔵庫 パン 発酵 – 冷蔵庫を使ったパン生地の長時間発酵のポイント、プロが教えるとっておきのやり方

オーバーナイト法の3つのメリット
この低温で長時間発酵させる、という方法にはとってもいいところがあります。
常温で発酵させていくやり方もありますが、それよりもちょっと違う面があります。
常温での発酵についてはこちらに書いてありますのでご参考にどうぞ。
パン 発酵 常温 – 天然酵母のパン生地を常温に置いて自然発酵してみよう ほったらかしパンの大体の目安は?ポイントを解説
天然酵母と相性がいい メリット①

天然酵母は市販で売っているドライイーストに比べて発酵がゆっくり進みます。
純粋な強い菌だけで作られているのではなく、
乳酸菌や酢酸菌などのそのほかの微生物も含まれているからです。
お米で言うと、白米じゃなくて玄米のイメージです。
玄米は外皮も胚芽も含まれているので白米とは味わいが違いますよね。
そんな感じで、天然酵母も他のものの作用で複雑なうまみが出ます。
長時間でゆっくりの発酵をさせていく、という意味でも
天然酵母のパン作りの工程にとても合っているのです。
ドライイーストの場合はこのオーバーナイトの方法で作るとき
思ったより早めに発酵してしまう可能性があります。
そこでイーストの量を減らす、といったことをします。
少量のイーストでゆっくり発酵を促すのです。
こねが控えめでもいいよ メリット②

通常に比べて入念にこねなくても大丈夫です。
グルテンは粉と水が一緒になったときに形成されていきますが、
時間をかけることによってこねが少なくてもうまく形成されていきます。
こねの良さは、こねることによってグルテンが強化されるのですが
長時間発酵では、そこまでのこね具合じゃない方が
この製法の良さが発揮できる気がしています。
うまみが出る メリット③

普通にやってもゆっくり発酵の天然酵母です。
低温にするとさらにゆっくりになってきます。
ゆっくり発酵すると言うことは菌がゆっくり活動します。
粉に含まれている糖類を時間をかけて分解していくのでその分、生地が熟成されていくのです。
小麦の香りも引き立てて香りも味もよくなるんですね。
オーバーナイトでパンを作る時の注意点
さて、今度はオーバーナイトで作る時の注意点をご説明していきたいと思います。
冷蔵庫に入れたけどうまく発酵しなかった、とか
焼いた時に膨らまなかった、とか
いろいろなお悩みを聞きます。
そんな失敗をしないように3つの注意点をあげてみたいと思います。
失敗しないオーバーナイト法 3つの注意点
冷蔵庫をうまく使う – ①

こね上がった生地は温かいですか?
手ごねの場合も機械ごねの場合も生地は温かくなっていると思います。
機械(ニーダー)を使った場合は特に温まっています。
夏場ではその傾向が強いです。
オーバーナイトをしようと思ったら(特に夏場)生地を冷蔵庫で少し冷やしてから
野菜室に入れます。
温度的には野菜室に一晩おいておきたいのですが、生地が温かいと
野菜室でもそのままどんどん発酵が進んでしまう場合がありますので
先に冷蔵庫(急ぐときは冷凍庫)に入れて少し温度を下げてから
野菜室に移します。
冬場は室温で温度を下げて野菜室に入れます。
(部屋が温かいときは冷蔵庫に入れるなど工夫してください)
生地を出してから温度の回復 – ②

オーバーナイトで失敗しやすいのが「発酵不足」です。
一晩置いたら生地の様子をみてくださいね。
ふんわりと生地が大きくなっていますか?
丸め直してみてガスが溜まっていますか?
まだまだ固いままだったら室温で発酵を促しましょう。
急ぎでなければもう少し野菜室に入れておきます。
上記に書いたようにいい状態になっていたら、
まずは室温に置いて生地の温度を回復させていきます。
ここですぐに成型、二次発酵と進んでいったらうまくいかなくなります。
生地の温度を回復させる
これ、とても大事です。
大きい生地のままでもいいし、分割して長めに休ませて(ベンチタイム)もいいです。
生地の消費期限 – ③
生地が熟成して発酵の状態がよくなったらどのくらい使えるでしょうか。
熟成が進んでいたら素早く使ってください。
しかし、まだの状態で保持されていたら
天然酵母の場合は生地の状態や材料にもよりますが、1週間くらいは持つものがあります。
生地の状態にもよる、と言いましたが見分けるにはちょっと慣れが必要ですので
様子を見ながらですが2〜3日中を目安にしてみてください。
ここでも「ふんわりしているか」「ガスが溜まっているか」見てくださいね。
とっても重要です。
いくつかの生地を作っておいて、出来上がりに時間差があると
少しずつ使っていくことができるようになります。
その間にいろいろな種類が楽しめるというわけです。
これは作り置き生地にもなるんですね!

ドライイーストの場合は24時間以内に使おう、といわれます。
天然酵母よりは消費期限は短いと思ってください。
ほったらかしの発酵で楽なパン焼きのおすすめ
冷蔵庫に入れておくだけのほったらかしパン。
一晩日をまたいでパンを焼いていくオーバーナイト法です。
ぱん蔵のレッスンで初めての方に一番最初に説明することでもあります。
そのときは「オーバーナイト」なんて言葉は使いませんが
「夜こねて朝、発酵しているというサイクルです」
と言っています。
(これは常温に置いて、という意味でレクチャーしていますが、暑い時期は野菜室に入れます)
その季節によって臨機応変に対応していくといいということです。
特に冷蔵庫の野菜室でゆっくりと発酵させていく方法は、生地の使える期間が長く
なりますのでお得な感じですね。
発酵は寝ている時間でもいいし、日中仕事をしていたり家事をしている時間でもOK。
ほったらかしでOK。
のんびりしててもいいのです^^

何をしていてもいいので自分の生活スタイルに合わせやすい。
忙しい方には特におすすめです^^
オーバー ナイト パン – オーバーナイト法の失敗しない3つの注意点 生地に旨味を出す製法のおすすめを天然酵母パン講師が解説します まとめ
いかがでしたでしょうか。
長時間で低温発酵させていく「オーバーナイト」という方法。
ゆっくり発酵させていくことで小麦本来の香りが生かされ、生地が熟成していくことによって
噛めば噛むほど味がでる、というパンになります。
まさに天然酵母のいいところを生かした形になりますね!
オーバーナイトをやる時の注意点は、
1冷蔵庫をうまく使う
2生地を出してから温度の回復
3生地の消費期限
これらに気をつけてぜひやってみてください。
冷蔵庫を使ったパンについてはこちらの生地もご参考にしてみてください。
こね ない パン – 冷蔵庫を使った「ほったらかし」でこねないパンは簡単に作れちゃう!上手に作る3つのコツを天然酵母パン講師が解説します